相続応用知識Q&A②回答
生命保険金の受取りは、原則として、特別受益に該当しません(最高裁平成16年10月29日判決)。
ただし、「特段の事情」がある場合には、民法903条1項の類推適用により,特別受益に準じて持戻しの対象になります。
上記特段の事情の有無については,保険金の額,この額の遺産の総額に対する比率のほか,同居の有無,被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係,各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断されます。
死亡退職金の受取りは、特別受益に該当するか否かは見解が分かれております。
★特別受益に該当するという審判例
死亡退職金については国家公務員退職手当法2条及び11条の趣旨からすれば、同規定による受給権者は固有の権利として右退職金を取得すると解するのが相当であるが、共同相続人間の実質的公平の見地からすると、やはり特別受益になるものと解すべきである(大阪家裁昭和51年11月25日審判)。
★特別受益に該当しないという審判例
受給権者が固有の権利として取得する死亡退職手当は、文理上民法903条に定める生前贈与、遺贈に該当せず遺留分減殺の対象にもならず、また、受給権者らが別に相続分に応じた相続財産を取得しても、それは被相続人の通常の意思に沿うものと思われること等を考慮すると、特別受益にはあたらないとするのが相当である(東京家裁昭和55年2月12日審判)(東京高裁平成10年6月29日判決)。
[まとめ]
①法律や就業規則などに死亡退職金の規定があり、受給権者の範囲が民法に定める相続人の範囲と異なっており、その定め方が遺族の生活保障の趣旨であり、その取得が被相続人の通常の意思に沿うものと思われる場合には特別受益に該当しない。
②遺族の生活保障の趣旨がない場合は、被相続人から相続人に対する遺贈と同様に考え特別受益とする。
特別受益財産による具体的相続分は、遺産分割審判手続きにおける分配の前提となるべき事項ですので、別個独立に判決によって確認を求めることはできません(最高裁判例平成12年2月24日判決)。
被代襲者の特別受益について代襲相続人がこれを持ち戻さなければならないかは判例・学説上争いがありますが、代襲相続人が、現実に利益を受けている限度で特別受益に該当するという見解が有力です(徳島家裁昭和52年3月14日審判)。
代襲相続人は、代襲原因発生前の特別受益について持ち戻さなければならないかどうかについては、特別受益制度は、共同相続人間の衡平の維持が目的ですので、受益の時期に関わらず、特別受益に該当するという見解が有力です(鹿児島家裁昭和52年3月14日審判)。
ただし、代襲相続人は、代襲原因が生じる前は相続人ではないため、特別受益に該当しないという審判例もあります(大分家裁昭和49年5月14日審判)。
受贈後に養子縁組によって推定相続人なった場合、特別受益に該当するかどうかについては、特別受益制度は、共同相続人間の衡平の維持が目的ですので、受益の時期に関わらず、特別受益に該当するという見解が有力です(神戸家裁平成11年4月30日審判)。
ただし、贈与が養子縁組のための支度金など、贈与と養子縁組との間に関連性がある場合には特別受益に該当するという審判例もあります(神戸家裁明石支部昭和40年2月6日審判)。
被相続人から相続人の配偶者や子などへの贈与等は原則として特別受益に該当しませんが、その相続人対する贈与と同視できるような特別の事情がある場合には、特別受益に該当します(福島家裁白河支部昭和55年5月24審判)。
被相続人は、遺言によって定めた割合による遺産を贈与する意思を持ち、その割合の増減は予想していないと考えられますので、常に持ち戻し義務を負わないという見解が有力です。
特別受益における婚姻のための費用は、持参金や支度金など婚姻のために被相続人から支出してもらった費用などです。
婚姻のための費用は、原則として特別受益に該当します。
しかし、金額が少額で被相続人の生前の資産及び生活状況に照らし、扶養義務の範囲内と認められる場合は、特別受益とはなりません(大阪家裁昭和38年9月18日審判・福井家裁昭和40年8月17日審判)。
挙式費用は社会生活上の役割からして、結納金については現在の社会慣行に照らせば相続分の前渡しとみられるほどの金額でないことが多いことから、特別受益に該当しないという見解が有力です。
共同相続人全員が同額の学資や婚姻費用を受けている場合には、特別受益は考慮しません(大阪家裁堺支部昭和38年9月18日審判)。
生計の資本としての贈与の具体例は下記のとおりです。
①不動産の贈与
子供が居住用の不動産を贈与した場合や、農家である被相続人が農地を子供に贈与した場合等です。
不動産は一般的に高額な財産ですから、生計の資本としての贈与と認められることが多いため、特別受益に該当します。
②金銭・動産等の贈与
金銭・動産等の贈与は、扶養義務の範囲内と認められない金額である場合には、特別受益に該当します。扶養義務の範囲内かどうかは、被相続人の資産状況、贈与の動機、贈与額、社会的地位及び生活状況などの諸事情を考慮して決定されます。
③借金の肩代わり
被相続人が、子供の代わりに借金を返済した場合には、「相続分の前渡し」として生計の資本としての贈与に該当します。
ただし、極めて少額な借金である場合には、特別受益に該当しません。
④高等教育のための学資
高等教育には、義務教育は含まれないのは当然ですが、現在の教育水準では、高等学校教育も義務教育に準じて、高等教育には含まれないと考えられております。
原則として、大学以上の教育が高等教育に該当します。
また、留学費用や留学と同視できる海外旅行の費用も同様です。
このような高等教育のために被相続人が支出した費用などは、原則として特別受益に該当します。ただし、被相続人の生前の資産状況、社会的地位及び生活状況に照らし、扶養義務の範囲内と認められる場合には、特別受益に該当しません(京都地裁平成10年9月11日判決)。
特別受益の評価の時期は、贈与の時の金額を相続開始の時の貨幣価値に換算した価額をもって評価します(最高裁昭和51年3月18日判決)。
ただし、遺産分割を行う場合には、相続開始時の相続分に特別受益の修正を行った相続分率を、遺産分割時の評価額に乗じて相続分を算出します。
相続開始時から遺産分割時までの期間が長い場合には、価額の変動がありますので、相続人間の公平の見地から遺産分割時の評価額で分配します(東京家裁昭和33年7月4日審判)。
贈与の目的物が受贈者の行為によらないで滅失したり、その価額の増減があった場合、その価格をその受贈者の相続分から控除するのは酷ですので、その受贈者は贈与を受けなかったものとして取り扱います。
贈与の目的物が受贈者の行為によらないで滅失した場合でも、それに代わる財産を取得した場合は、その価額を評価して特別受益の対象にすべきだと考えられております(大阪地裁昭和40年1月18日判決)。
贈与の目的物が受贈者の行為によって滅失したり、その価額の増減があった場合は、その目的物が相続開始時に原状のままあるものとみなします(民法第904条)。
「受贈者の行為によって」とは、受贈者の過失も含むと解されております。
「滅失」には、焼失、破壊などの事実行為による物理的滅失のほか、贈与・売買などの法律行為による経済的滅失も含みます。
また、農地を宅地に造成しても、農地のままあるとみなして、相続開始時の価額で評価します。
特別受益者の相続額=(相続開始時の財産価額+贈与財産の価額)×相続分-遺贈・贈与の価額
※相続開始の時の財産価格に贈与財産の価額を加算しますが、遺贈の価額は相続開始の時の財産価格に含まれておりますので、みなし相続財産を算定する際に加算する必要はありません。
[計算例]
長男C
二男D
(9,000万円+3,000万円)×1/6-1,000万円=1,000万円
三男
(9,000万円+3,000万円)×1/6=2,000万円
※特別受益額が相続分を超えている超過特別受益者は、相続開始時の遺産から相続分を取得できませんが、その超過分を返還する必要はありません。
超過特別受益者がいる場合の具体的相続分の計算方法には、①具体的相続分基準説と②本来的相続分基準説に審判例が分かれております。
被相続人が特定の相続人に相続分以外に財産を取得させる意思を有していたことが推測できる事情がある場合には、黙示意思表示によって持戻しを免除することができます(高松家裁丸亀支部昭和37年10月31日審判)。
黙示意思表示によって持戻しを免除が認められた事例として、
①農家である被相続人が、家業を承継する三男に相続分を超える農地を生前贈与した事例(福岡高裁昭和45年7月31日決定)
②妻としての貢献に報いるため、老後の生活の安定を図るため、妻に対し不動産の贈与をした事例(東京高裁平成8年8月26日決定)
などがあります。
代襲者は被代襲者が取得すべき相続分を取得するものであり、その相続分の中には一体化したものとして寄与分が含まれると考えられますので、代襲者は被代襲者の寄与分を主張できます(横浜家裁平成6年7月27日審判)。
代襲者は代襲原因が生じる前の寄与でも、共同相続人間の衡平を図る寄与分制度の趣旨を重視して、遺産分割時に相続人の資格を有していれば寄与分を主張できると解されております(通説)。
相続人の配偶者や子供の寄与であっても、それが相続人の手足となってあるいは履行補助者となって貢献したような場合には、相続人の寄与度同視できることから、相続人の寄与分として考慮することができます(東京高裁平成元年12月28日決定)。
寄与分制度は共同相続人間の公平を図ろうとするものであるから、相続人が先妻である母親の寄与を主張できるという見解があります(東京高裁平成元年12月28日決定)。
しかし、これを認めれば、現行法上配偶者に代襲相続を認めていないにも関わらず、配偶者に代襲相続を許すのと実質的に同じになるため、認めるべきでないという見解が有力です(通説)。
家業従事型の寄与行為の中でも、農業経営における寄与の事例が最も多いです。
審判例として
30年間農業に従事した妻に1,000万円、約8年間にわたって事実上農業後継者として農業に従事した養子に500万円の寄与分を認めた事例(前橋家裁高崎支部昭和61年7月14日審判)があります。
その他の家業として、
①家業である製造業を約12年間無報酬で手伝い、遺産の維持・増加に貢献した長男に、生前に購入された家屋について、共有の趣旨を参酌して5割の寄与分を認めた事例(大阪家裁昭和40年9月27日審判)
②経営の維持拡大に貢献した二女夫婦に対して、労務を出資する趣旨の一種の組合契約が存在したと認定し、財産形成の寄与割合を各3分の1と認定した事例(東京高裁判例昭和51年5月27日判決)
③寄与行為は原則として無償でなければなりませんが、無報酬でなくても、薬局を会社組織にし、店舗を新築するなどで経営規模を拡大したことが寄与にあたるとして、遺産の3割を寄与分と認めた事例(福岡家裁久留米支部平成4年9月28日審判)
などがあります。
寄与分の算定方法の具体例として、下記のような審判例があります。
①家事従事型の寄与の算定が困難であることから、総合的な算定方式を採用した事例。
30年間農業に従事した妻に1,000万円、約8年間にわたって事実上農業後継者として農業に従事した養子に500万円の寄与分を認めた事例(前橋家裁高崎支部昭和61年7月14日審判)があります。
②農業に従事した貢献度を、合理的に算定した労務対対価(給与相当額)よりその期間における寄与者の生活費相当額を控除して算定した事例(東京高裁昭和54年2月6日決定)
③寄与時の農作業標準賃金を認定し、それに作業日数を乗じ、それから生活費相当がとして40%を控除して寄与分を認めた事例(盛岡家裁一関支部平成4年10月6日審判)
共働きの夫婦が、婚姻期間中に得た財産が被相続人名義になっていたとしても、実質は共有に属するとして、配偶者に5割の寄与分を認めた事例があります(大阪家裁昭和59年1月25日審判)。
したがって、共働きの夫婦の場合、収入比率に近い寄与分が認められることになります。
夫婦間又は親族間で、療養看護が寄与分として認められるには、協力扶助義務・扶養義務を超える程度の寄与である必要があります。
特に、配偶者の協力扶助義務は、他の親族間のそれよりも高度であることから、配偶者の寄与分が認められるためには、相当高度な貢献が必要になります。
寄与分として認められた事例として、以下のような審判例があります。
①重い老人性痴呆症の母を10年に渡って介護した娘に、職業付添婦に支払うべき費用の6割を認めた事例(盛岡家裁昭和61年4月11日審判)
②老人痴呆が進行し昼夜問わず療養看護が必要になった被相続人を看護した養女に、家政婦賃金の基本料金に超過料金及び深夜料金を加えた額に看護日数を乗じた額を寄与分と認めた事例(盛岡家裁一関支部平成4年10月6日審判)
③28ヶ月間、寝たきりの被相続人に対して献身的な看護をした寄与相続人の妻の貢献を認め、月額3万円~9万円を看護期間で乗じた120万円を寄与分として認定した事例(遺産額約850万円)(神戸家裁豊岡支部平成4年12月28日審判)
遺産額や看護期間に応じて、寄与分額を算定する審判例が多いようです。
扶養型の寄与分は認められか否かは争いがありますが、認められるという見解が有力です。
認められるという審判例は、下記のとおりです。
二男が被相続人の扶養を全面的に引き受けた事例で、二男が被相続人の扶養を全面的に引き受けたからこそ、被相続人が自己の財産を消費しないで遺産として残せたのだから、寄与相続人が負担した扶養料を共同相続人の数で除した金額を他の相続人の負担すべき金額として寄与分を認めました(大阪家裁昭和61年1月30日審判)。
財産管理型の寄与は、被相続人の財産を管理することによって財産の維持形成に寄与した場合ですが、様々な形態があります。
認められた審判例は、
①被相続人所有の土地の売却に際し、立退交渉、家屋の取り壊し、売買契約の締結などに努力したとして、土地価格の増加に対する寄与分が、不動産仲介人の手数料基準を考慮して認められた事例(長崎家裁諫早出張所昭和62年9月1日審判)
②被相続人が遺産不動産に係る訴訟第1審に敗訴した後、証拠収集に奔走した相続人の行為は、控訴審において逆転勝訴の結果を得ることに顕著な貢献があり、遺産の維持について特別な寄与があったとして、遺産額約5億3,600万円の1割を寄与分と認めた事例(大阪家裁平成6年11月2日審判)
などがあります。
被相続人Aが死亡し、相続人が、妻Bと子Cのケースで、
BがAの相続に関し相続を放棄したが、その後、Cが死亡し、Cの妻とBが相続人なった場合、BがAの相続に関し相続を放棄したことが特別の寄与にあたるという見解が有力です。
寄与者が推定相続人になる前にした貢献であっても、民法が特に寄与の時期を限定しておりませんので、寄与分として認められます(通説)。
寄与分に関する民法の規定は、相続開始時を基準として、みなし相続財産を定めておりますので、相続開始後の貢献を、寄与分として主張できません(東京高裁昭和62年9月1日決定)。
相続開始後に相続人が遺産の維持管理した場合、他の相続人との関係では不当利得あるいは事務管理等の法理に従って処理されることになります。
寄与分は実質的には寄与者の財産であるものを取得させるものですので、民法の規定では上限はありません。
過去の審判例を見ても、遺産の2分の1程度が最大限となっているので、他の相続人保護で上限をおく必要はないからです。
寄与分は、相続開始時を基準として具体的相続分を算定するころから、相続開始時を算定評価の時期とする裁判例が大多数です。
しかし、寄与分を算定するには、協議や審判などが必要であり、遺産分割の対象となる財産は、遺産分割時を基準として評価しますので、実務的には、遺産分割時を基準として評価することになります(新潟家裁昭和34年6月3日審判)。
寄与相続人のみの場合の相続分の算定方法は、被相続人が相続開始時有していた財産から寄与分額を控除したものを相続財産とみなして、各相続人の相続分を算出し、寄与相続人についてはこの相続分に寄与分を加えた額を相続分とします(民法第904条の2)。
[前提事実]
相続人:妻A、子B、子C
遺産額:3,000万円
[算定方法]
A (3,000-500)×1/2=1,250万円
B (3,000-500)×1/4=625万円
C (3,000-500)×1/4+500=1125万円
寄与分相続人と特別受益相続人が併存する場合の優先関係については、民法に規定がありませんが、同時に適用して算定する考え方が有力です(大阪家裁昭和61年1月30日)。
上記の見解を採用すれば、各相続人間の公平を図れますし、計算方法も簡便的ですので、妥当な方法だと思われます。
遺産分割の審判の申立てとは別に寄与分を定める審判の申立てができません(民法第904の2条4項)。
原則として、寄与分審判の申立ては、遺産分割審判の申立てと同時にしなければなりません。
家庭裁判所は、遺産分割審判の申立てのみがされた場合、相続人が寄与分を定める審判の申立てをすべき期間を定めることができます(家事審判規則第103条の4)
この場合において、その期間は、1ヶ月以上でなければなりません。
したがって、家庭裁判所が、寄与分審判の申立てをすべき期間を定めた時は、原則として、その期間内に申立てをしなければなりません。
寄与分は、相続分の修正要素として主張するのであるから、行使上の一身専属権とまでいえないことから、相続分の譲渡により、当然譲受人に承継されるという見解が有力です(通説)。
寄与相続人の相続人(再転相続人)は、寄与相続人の相続分を主張できますので、寄与相続人が寄与分を請求したか否かに関わらず、寄与分を主張できます(通説)。
したがって、寄与分を相続することができます。
寄与分は、相続分の修正要素であり、相続分と離れて存在し得ないものですので、寄与分のみ譲渡することはできません。
寄与分は、共同相続人間の協議や審判によって定まりますので、被相続人が遺言で寄与分を定めても法的に拘束力はありません。
遺言によってできる行為は法定されており、法定事項以外は法的拘束力がないからです。
しかし、「相続人Aに甲土地を寄与分として与える」と記載されていた場合、特定遺贈として効力を有することになります。
民法上、寄与分と遺留分の優先関係については規定がありませんが、遺留分を侵害する寄与分は認めるべきでないという見解が有力です(東京高裁平成3年12月24日決定)。
寄与分は、共同相続人間の協議や家庭裁判所の審判に定められるものですので、遺留分減殺請求訴訟において、寄与分を抗弁として主張できません(東京高裁判例平成3年7月30日判決)。
相続分を一部譲渡することはできないという見解が有力です。
相続分は、相続人が遺産全体に対して有する包括的持分又は法律上の地位であり、共有持分とは異なるからです。
また、一部譲渡を認めると、遺産分割に参加する人が増えて、相続関係が複雑になることも理由としてあげられます。
相続分の譲渡は、相続財産に属する個別的財産権の移転ではありませんので、債権譲渡の対抗要件に関する規定の適用を受けません(東京高裁昭和28年9月4日決定)。
したがって、先の相続分の譲渡が有効になされた場合、後の譲渡は無効となります(新潟家裁佐渡支部平成4年9月28日審判)。
相続分の譲受人は相続債務を負担することになります。
問題は、相続債権者との関係においてどのように債務を負担することになるか見解が分かれております。
債務引受の考え方からすれば、内部的には譲渡人から譲受人へ債務が移転しますが、相続債権者との関係では譲渡人が債務を負担することになります。
学説の中には、譲渡人と譲受人が連帯類似の負担することになるという考え方もあります。
私見としては、債務引受と同様の考え方で良いと思います。
相続分が譲渡された場合、譲渡人の共同相続人として有する一切の権利義務は包括的に譲受人に移転しますので、譲渡人は、遺産分割手続きに参加することができなくなります(大阪高裁昭和54年7月6日決定)。
したがって、遺産分割手続きは、譲受人が参加することになります。
民法上、相続分の譲渡が認められているのと異なって、民法第915条所定の相続放棄以外に相続分の放棄は認められておりません。
相続分の放棄を認めてしまうと、相続放棄の規定が無意味になってしまうからです。
しかし、プラス相続分の取得を望まない相続人がいるケースもあります。
この場合には、相続分の放棄を共有持分の放棄と捉えて、相続財産の共有持分を放棄することができます(東京家裁昭和61年3月24日審判)。
上記の場合、共有持分の放棄ですので、放棄者も相続債務は負担することになります。
不動産の登記手続きをするには、一旦、共同相続人全員名義に移転登記をして、その後、放棄者の持分を他の相続人へ相続分に応じて移転する手続きをします(昭和6年10月3日民事997号民事局長回答)。
[税務上の注意点]
相続分の放棄を、他の相続人へ贈与税が課税される可能性がありますので、相続分の譲渡で対応できるのであれば、相続分の譲渡の方が手続き上簡便的だと思います。
遺産相続により相続人の共有となった財産の分割については、遺産分割審判によるべきであり、通常裁判所に共有物分割請求の訴え提起することはできません(最高裁判例昭和62年9月4日判決)。
理由は、遺産の共有は一定の身分関係に基づいて必然的に発生するものですので、遺産全体として包括的に分割すべきであるとの強い要請があるからです。
預金などのように分割できる金銭債権は、各相続人の法定相続分に応じて当然に分割されますので、遺産分割協議をするまでもなく、自己の相続分に応じた払戻し請求をすることができます(最高裁判例昭和29年4月8日判決、最高裁判例平成16年4月20日判決)。
したがって、原則として、遺産分割の対象になりません。
しかし、相続人全員の合意がある場合には、遺産分割の対象になります(東京高裁平成14年2月15日決定・福岡高裁平成8年8月20日決定)。
[銀行実務の取り扱い]
銀行などの金融機関の実務上の取り扱いは、相続人からの法定相続分に応じた預金の払戻請求に応じておりません。
銀行としては、二重払いの危険がある、相続人間の紛争に巻き込まれたくないなどの理由で、上記の様な取扱いをしているようです。
したがって、実務上、払戻し請求するには、①銀行所定の払戻請求書に相続人全員が実印を押印して印鑑証明書を添付して払戻し請求するか、②遺産分割協議書に相続人全員が実印を押印して印鑑証明書を添付して払戻し請求する必要があります。
現金(金銭)は遺産分割の対象になります(最高裁判例平成4年4月10日判決)。
したがって、相続財産である現金(金銭)を相続開始時に保管している相続人に対して、他の相続人は、自己の相続分に相当する金銭の支払いを求めることができません。
定額郵便貯金は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されません(最高裁判例平成22年10月8日判決)。
理由としては、郵便貯金法7条1項3号は、定額郵便貯金につき、一定の据置期間を定め、分割払戻しをしないとの条件で一定の金額を一時に預入するものと定めて、預入金額も一定の金額に限定しているからです(同条2項、郵便貯金規則83条の11)。
同法の趣旨は、多数の預金者を対象とした大量の事務処理を迅速かつ画一的に処理する必要上、預入金額を一定額に限定し、貯金の管理を容易にして、定額郵便貯金に係る事務の定型化、簡素化を図ることにあります。
相続債務も相続債権と同様に、相続分に応じて分割承継されるものですので、遺産分割の対象になりません(東京高裁昭和30年9月5日決定・大阪高裁昭和31年10月9日決定)。
しかし、相続人全員で、相続債務について特定の相続人が債務引受することは、債権者の承諾を得ること条件として有効です。
相続人が相続債務を立替弁済した場合、遺産分割審判において償還を求めることはできません(大阪高裁昭和31年10月9日決定)。
相続債務の立替弁済の償還は、通常の民事訴訟手続きによるべきだからです。
相続開始後、相続財産の売却等によって生じた財産(代償財産)は、共同相続人全員で遺産分割の対象とする合意がある場合を除いて、相続財産に含まれません(最高裁判例昭和54年2月22日判決)。
代償財産は、遺産分割の対象たる相続財産から逸出しますので、各相続人は、自己の相続分に応じた代償財産の取得や引渡しを請求することになります。
相続開始から遺産分割までの賃料債権は、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得しますので、後にされた遺産分割の影響を受けません(最高裁判例平成17年9月8日判決)。
相続開始から遺産分割までの賃料債権は、共同相続人全員の合意がある場合には遺産分割の対象にできるという見解が有力です(東京高裁昭和63年1月14日決定)。
遺産の管理費とは、相続開始後の遺産の維持管理に要した費用で、例えば、固定資産税、公租公課、火災保険料などです。
これらの費用については、その金額が明確で、共同相続人全員が遺産分割手続き内で清算する同意しているような場合には、遺産分割審判手続きで考慮できるという見解が有力です(広島高裁松江支部平成3年8月28日決定)。
葬儀費用は実質的な葬儀主宰者(喪主)が負担すべきですので、遺産分割審判において考慮すべきではないという見解が有力です(東京地裁判例昭和61年1月28日判例)。
遺産分割審判の基準は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮します(民法第906条)。
また、大阪高裁昭和51年2月19日決定では、
遺産分割は単に算術的に正確に相続分に応じた分割が行われるのではなく、「具体的な公平」な分割を行うべきであるとしております。
上記は、遺産分割審判の基準ですので、相続人間の協議で、特定の相続人の相続分をゼロとする遺産分割協議も有効です。
遺産分割審判は、各相続人の相続分にかなうようにしなければなりませんので、相続分を変更することはできません(東京高裁昭和37年4月17日決定)。
しかし、相続人が取得する財産の一定時点における評価額の対比が相続分に完全に一致しなくても、相続分に準拠していれば、有効な遺産分割と言えます(東京家裁昭和44年2月24日審判)。
具体的遺産の取得に関する相続人の意向や希望は考慮させる余地はあると言われております。
相続人の意向や希望は、自身の遺産取得に関するものであり、他の相続人が何を取得するかとういう意向や希望ではありません。
遺産の取得を希望しない相続人に対して、その遺産を取得させることは原則として相当ではないと考えられております。
祭祀財産は、相続とは別個に承継されますので、祭祀財産を遺産分割において考慮することはできません(東京高裁昭和28年9月4日決定)。
また、祭祀承継者の相続分を増加させたり、遺産の中から祭祀料として特別の財産を取得させることはできません。
①現物分割
②代償分割
③換価分割
④共有分割があります。
優先順位も上記の順序となります。
したがって、共有分割をするには、①~③までの方法を採用できない事情が存在しなければなりません。
遺産分割審判で代償分割するために、「特別の事由」が必要になります(家事審判規則第109条)。
「特別の事由」とは、①現物分割が相当でないこと、②遺産を取得する相続人に代償金の支払能力があることです(最高裁平成12年9月7日決定)。
なお、審判と違って、相続人全員の協議によって、代償分割を定めることは自由です。
代償金の支払は、即時になされるのが原則ですが、即時に支払えないケースあります。
そういう場合には、債務額、支払期間、当事者双方の利益などの一切の事情を考慮して、分割払いを命じることもできます(東京高裁昭和53年4月7日決定)。
また、その場合には、利息を付加してすべきである見解が有力です(東京家裁昭和55年2月12日審判)。
代償金が分割払いになった場合、抵当権設定登記手続きを命ずることはできないという見解が有力です。
抵当権設定登記手続きを命ずるには、本来地方裁判所の給付訴訟手続きが必要であって、家庭裁判所の形成処分には、抵当権設定登記手続きまで認める趣旨ではないと解されているからです。
しかし、少数ながら抵当権設定登記手続きを命じた審判例もあります(東京家裁和44年3月27日審判)。
遺産分割審判において、代償金の支払いを命じられた相続人が、代償金の支払いを受ける相続人に対する債権を反対債権として相殺することはできません(大阪高裁平成10年6月5日決定)。
相殺の意思表示は、審判確定まで効力を生じないため、遺産分割審判において、相殺したものと扱うことはできないからです。
換価分割には、①終局審判において売却を命じる場合と、②中間処分として売却を命じる場合があります(家事審判法第15条の4、家事審判規則第108条の3)。
任意売却を命ずることができるのは、中間処分としての換価する場合のみです。
また、任意売却を命ずるには、相続人全員の同意が必要です。
家庭裁判所は、遺産の分割の審判をするため「必要があると認めるとき」は、相続人に対して、遺産の全部又は一部について競売し、又は任意売却を命ずることができます(家事審判法第15条の4、家事審判規則第108条の3)。
「必要があると認めるとき」とは、
①現物分割が著しく困難であり、かつ、現物分割をすればその価額を著しく毀損させることになること。
②代償金の支払い能力のある相続人がいないこと。
などです(新潟家裁三条支部昭和41年12月8日審判)。
遺産の一部について換価する場合、換価が完了してはじめて遺産額が確定するため、遺産分割審判時に遺産額が確定しないことから、遺産分割方法の定め方が困難であるという問題点があります。
この場合には、換価する遺産と他の遺産を区別して、分配方法を定めるという見解が有力です。
換価する遺産と他の遺産を区別することに不相当な事情がある場合には、中間処分として換価するのが妥当だと思われます。
換価人は、相続人の中から選任されます。
換価人は、遺産の換価について相続人の代理人として、競売申立てや、任意売却においては売買契約の締結などを行います。
ただし、管理人が選任されても、相続人は、その遺産の処分権を失うわけではありません。
共有分割が認められる場合は、現物分割、代償分割、換価分割が相当でない事情があり、共有分割にしても分割に支障がないようなケースです(札幌家裁平成10年1月8日審判、大阪高裁平成14年6月5日決定)。
したがって、共同相続人間の感情的対立が激しい場合に共有分割をすると、紛争の解決を先送りにすることになるためは相当ではないということになります(東京高裁平成2年6月29日決定)。
共有分割がされると、民法の共有に関する規定の適用を受けるため、後日、共有状態を解消するには、共有物分割の手続きによることになります(東京地裁判例昭和45年2月16日判決)。
特別の事情がある場合には、遺産分割審判において使用借権や賃借権の設定を命じることができるという見解が有力です(福岡高裁昭和43年6月20日決定)。
例えば、
土地と建物をそれぞれ別の相続人名義にしなければならない事情ある場合に、建物を取得する相続人のために使用借権等を設定する様なケースです(高松高裁昭和45年9月25日決定)。
しかし、使用借権等を設定できるのは、農地法などの特別の規定がある場合であって、特別の規定がない遺産分割審判では、使用借権等を設定は認めるべきではないという見解もあります(盛岡家裁昭和42年4月12日審判)。
遺産の評価は、原則として行う必要があります。
遺産分割は、遺産を構成する個々の財産を、各共同相続人間に、それぞれ具体的相続分に応じて分配する手続きですので、これが適正衡平になされるためには、遺産を正当に評価が必要になります
遺産の評価をしないでなされた審判は違法とされております(大阪高裁昭和26年3月23日決定)。
遺産の評価は、遺産分割時を基準として評価します(福岡高裁昭和40年5月6日決定、新潟家裁昭和34年6月3日審判)。
遺産分割審判の手続きでは、審理がなされる直近の時点です。
具体的には、証拠調べ終了時ということになります。
遺産審判の抗告審の段階では、遺産の再評価をする必要はありません(東京高裁昭和63年5月11日決定)。
遺産分割はできるだけ相続開始時に接着した時点でなされるのが望ましいことから、遺産分割の時点を長期に遅らせることにより、相続開始後に遺産分割した場合と比較して著しく異なる結果になることは好ましくないからです。
相続人の主観的な価値は、遺産の評価に反映させることはできません。
善、お椀などの相続財産で、相続人が特別に愛情を持っていたとしても、使用価値、交換価値がほとんどない場合には、遺産分割の対象になりません(高松高裁昭和36年1月8日決定)。
いかなる資料に基づいて遺産の評価額を認定するかは、裁判所の自由裁量になりますので、相続人の意見を聞かなければならないわけではありません(福岡高裁昭和40年9月27日決定)。
しかし、遺産が高額な場合や相続人間の対立が激しい場合には、相続人の意見を聴衆することになると思われます。
不動産の評価するにあたって必ず鑑定が必要なわけではありません。
しかし、不動産の評価は不動産鑑定士などの専門家でないと困難な面があり、評価額が高額になることから、原則として、不動産鑑定士によって鑑定評価することになります。
固定資産税評価額は、不動産の客観的交換価値を必ずしも反映していないですし、時価よりも低額であるのが通例ですので、原則として、固定資産税評価額で遺産を評価することはできません(福岡高裁平成9年9月9日決定)。
遺産である不動産を固定資産税評価額で評価することが許されるのは、特別な事情がある場合です。
特別の事情として認められたものとして、下記のような事例があります。
①相続人全員に現物を分割取得させる場合で、各物件の評価にあたり、固定資産税評価額を基準として各相続人の相続分に応じた評価比によって分割する場合には公平に失するとは言えない(大阪高裁昭和46年12月7日決定)。
②土地が遺産の大部分を占めている場合には、各土地の価値の大小を見定める尺度として利用するのであれば差し支えない(東京高裁昭和49年9月13日決定)。
③相続全員が同意し、著しい不衡平をもたらさない場合で、かつ、鑑定をすれば莫大な費用がかかり相続人がそれを望んでいない場合には、固定資産税評価額に基づいて評価することも許される(鹿児島家裁昭和43年7月12日審判・東京家裁昭和48年12月11日審判)。
遺産に不動産がある場合、不動産鑑定士などの専門的知識を有する人が参与員に選任されることが一般的です。
この場合、その参与員の意見によって遺産である不動産を評価できるかが問題となります。
参与員は、意見を述べるにあたって、通常の鑑定においてされるほどの資料の収集を行わないのが一般的ですので、特別の事情がない限り、参与員の意見のみで遺産である不動産を評価することはできません。
特別の事情として認められた事例として、
相続人全員の合意があり、鑑定費用の予納や負担をめぐって相続人間で紛争が生じ、鑑定の実施が困難な場合(名古屋高裁平成8年7月29日決定)
などがあります。
不動産鑑定士による鑑定評価がなされても、鑑定方法に誤りがあり公平な遺産分割が実現されていない場合には、抗告審において取消すことができます(大阪高裁昭和49年9月17日決定)。
鑑定費用は国庫立替えが原則ですが(家事審判規則第11条)、実務上は、通常当事者から任意の予納を求めるのが原則になっています。
相続人が鑑定費用を予納しない時は、不動産であれば、固定資産税評価額を基準として評価することも許されると言われております。
鑑定費用を予納がない場合の審判例の中では、不動産鑑定士の資格を持つ参与員の意見を聴いて時価を認定したものがあります(高知家裁昭和57年8月30日)。
不動産の鑑定評価の方法には、①原価方式、②比較方式、③収益方式の3つがあります。
実務上は、上記の3つの方法を組み合わせて行われております。
①原価方式:不動産の再調達に要する価格に着目して価格を求める方式
②比較方式:市場における実際の取引事例に着目して価格を求める方式
③収益方式:不動産を利用することによって得られる収益に着目して価格を求める方式
[賃借権]
更地価額に対する割合によって評価するのが一般的です。
土地の所在地、住宅地、商業地といった土地の用途、非堅固建物・堅固建物などによって割合が変わってきます。
相続税を計算する際に利用する路線価の借地権割合が参考になります。
[使用借権]
土地の使用借権は、更地価額の1割~3割ぐらいで評価するのが多いです。
裁判例には、相続人の1人が店舗を建築して長期間営業を継続しているなどの事情を考慮して、使用借権の価格を更地の3割としたものがあります(東京高裁平成9年6月26日決定)。
抵当債務が相続債務である場合には、抵当債務は各相続人が法定相続分に応じて法律上当然負担することになりますので、不動産を評価するにあたり、抵当債務は控除されません(神戸家裁明石支部昭和40年2月6日審判)。
抵当債務の弁済に伴う求償関係は、遺産分割における担保責任の問題として処理されます。
また、抵当債務が相続債務でない場合にも、同様と考えられております。
不動産を評価するにあたって、相続開始前から居住する相続人の「居住利益」を考慮して家屋の評価額から控除すべきであるという裁判例があります(大阪高裁昭和54年8月11日決定)。
しかし、居住の利益を考慮する事例の多くは配偶者の居住権の保護にありますが、昭和55年の民法改正で配偶者の相続分が引き上げられ寄与分制度が設けられたことから、居住の利益を評価する必要性はなくなったという見解が有力です。
したがって、相続人が相続開始前から居住していた事情は、遺産分割方法を考慮するに際し、その相続人に家屋を取得させるべき有力な要素にとどまることになります。
農地の評価方法は、収益方式による裁判例がほとんどです。
しかし、近い将来宅地に転用される可能性が高い農地の場合には、時価方式により宅地として評価することになります(大分家裁中津支部昭和51年4月20日審判・東京高裁昭和39年6月26日決定)。
上場株式:取引相場が時価を反映しているため、相場価格によって評価する。
非上場株式:非上場株式は他に譲渡されないため、交換価値の把握が困難です。
具体的な評価方法では、
会社法上の株式の買取請求における価格の算定、
税務署の財産評価通達に基づく価格の算定(新潟家裁昭和34年6月3日審判)
などがあります。
なお、税務署の財産評価通達に基づく価格の算定には以下の方法があります。
①純資産評価方式
②収益還元方式
③配当還元方式
④類似業種比準方式
⑤上記①~④を組み合わせた複合方式
のれんとは、得意先・仕入先関係・創業の年代・地理的関係・営業上の秘訣・経営の組織・販売の機会などの営業の固有の事実関係であって財産的価値あるものをいいます。
のれんは、単なる事実関係ですので、直接には相続の対象になりませんが、営業上の利益の源泉となり、財産的に評価すれば相当の価値を有します。
したがって、のれんを遺産の対象外にすると、公平な遺産分割ができない可能性がありますので、遺産に取り込んで遺産を分配すべきであると解されております。
問題は、のれんの評価方法ですが、相続税計算上の評価方法が参考になります(財産評価基本通達165)。
遺言で共同相続人一人に遺産分割方法の指定を委託することはできません(東京高裁判例昭和57年3月23日判決)
相続させる旨の遺言における遺言利益の放棄できないという見解が有力です(東京高裁判例平成21年12月18日判決)
理由としては、遺言により被相続人の相続開始時に、不動産の所有権を何らの行為を要しないで相続により確定的に取得するからです。
特定の不動産を特定の相続人に相続させる旨の遺言と異なる遺産分割をすることができます(東京地裁判例平成13年6月28日判決)。
しかし、遺言の即時移転効により、遺産は共有状態にはなりません。
したがって、当事者による遺産分割協議は、取得分の贈与もしくは交換的譲渡となります。
この場合、税務上、贈与税や譲渡所得税の問題が生じる可能性がありますので注意が必要です。
相続人の1人に遺産の全部を遺贈する旨の遺言書がある場合でも、相続人全員で遺言の内容と異なる遺産分割をすることができます。
この場合、受遺者である相続人が遺贈を事実上放棄し、共同相続人間で遺産分割が行われたと考えられますので、受遺者である相続人から他の相続人に対して贈与があったものとして贈与税は課税されません(国税庁質疑応答)。
相続分が譲渡された場合、譲渡人の共同相続人として有する一切の権利義務は包括的に譲受人に移転しますので、譲渡人は、遺産分割協議に参加することができなくなります(大阪高裁昭和54年7月6日決定)。
したがって、遺産分割協議は、譲受人が参加することになります。
包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有します(民法第990条)。
したがって、遺産の一部について包括遺贈があった場合、包括受遺者は相続人と遺産分割協議をし、共有関係を解消することになります。
相続人が児童福祉施設に入所中の未成年者の場合、児童福祉施設長は、未成年者のために遺産分割協議をすることができます(昭和42年12月27日民事甲3715号民事局長回答)。
子供がいない夫婦が、夫(A)、妻(B)の順に死亡し、Aの相続人はB・C・Dであり、Bの相続人がE・Fの場合、C・D・E・F間で、Cが遺産である不動産を取得する旨の遺産分割協議をすることができます(昭和27年7月30日民事甲1135号民事局長回答)。
Bの相続人であるE・Fは、BがAの遺産について遺産分割できる地位を承継しているからです。
親権者が数人の子を代理して遺産分割協議をすることは、たとえ、数人の子のいずれの衡平を欠く意図がなくても利益相反行為に該当しますのですることはできません(最高裁判例昭和48年4月24日判決・最高裁判例昭和49年7月22日判決)。
親権者が未成年者である数人の子のために特別代理人を選任する場合には、数人の子ごとに特別代理人を選任しなければなりません(最高裁判例昭和49年7月22日判決)。
例えば、親権者である父と子が利益相反する場合、母が単独で子を代理できるかが問題となります。
最高裁は、そういう場合、母と特別代理人が共同で子を代理する必要があると判示しております(最高裁判例昭和35年2月25日判決)。
相続人の一人が全て取得する旨の遺産分割協議は有効です(昭和28年4月25日民事甲697号民事局長通達・熊本地裁判例昭和30年1月11日)
相続人全員で合意するのであれば、実質相続放棄と同様の結果を生じる場合であっても、任意に定めることができます。
遺産分割協議は持ち回りの方法で行うことができます(東京高裁判例昭和59年9月25日判決)。
各相続人が遠方に住んでいる場合、実務上、「遺産分割証明書」という書類を作成し、各相続人に押印していただきます。
一枚の遺産分割協議書ではありませんが、各相続人に遺産分割協議が成立したことをそれぞれ証明してもらい、全部揃って、一枚の遺産分割協議書と同様の効果を生じさせるものです。
相続人の1人であるAが遺産である不動産を取得し、Aは自己の固有の不動産を他の相続人Bに与えることができます(昭和40年12月17日民事甲3433号民事局長回答)。
この場合の、所有権移転登記の登記原因は、「遺産分割による贈与」となります(登記研究528-184)。
遺産分割協議を同じ代理人によってすることは、原則としてできません。
しかし、本人の同意があれば双方代理も許されますので、遺産分割協議書上でその旨が明らかであれば遺産分割協議を同じ代理人によって行うことができます(昭和37年11月21日法曹界決議)
各相続人ごとに作成・調印した遺産分割協議書でも、相続人全員の合意が整ったことが全部合わせることによって確認できるのであれば、その遺産分割協議書は有効です(昭和35年12月17日民事甲3327号民事局長回答)。
遺産を処分・消費してしまいそうな相続人がいる場合には、遺産分割調停の申立後、調停員会又は家事審判官に仮の措置を求めることになります(家事審判規則第133条)。
あくまでも、調停委員会等の職権で命じられるものですので、当事者に申立権はありませんが、仮の措置を求めるともによって発動を促します。
一般的には民事調停法第12条の
相手方その他の事件の関係人に対して、現状の変更又は物の処分の禁止その他調停の内容たる事項の実現を不能にし又は著しく困難ならしめる行為の排除を命ずることになります。
裁判例では下記のような事項を命じております。
①相続人全員に家賃の取立てを禁止し、第三者である銀行を家賃の取立人とした事例(福岡家裁昭和33年7月14日命令)
②建物の新築工事の中止を命じた事例(大阪家裁昭和35年8月23日命令)
③遺産である家屋から退去、相続財産・果実の搬出、売却その他の処分の禁止を命じた事例(新潟家裁六日町支部昭和36年11月18日命令)
④農地の耕作の妨害を禁じた事例(青森家裁昭和49年5月13日命令)
遺産分割調停前の仮の措置には執行力はありません。
仮の措置を命じられた相手方が、正当な理由なくそれに従わない時は、家庭裁判所は科料の制裁を課すことができます。
したがって、間接的な強制力しかありませんので、調停前の仮の措置を命じる事例は少ないようです。
家事審判法第15条の3では、審判の申立てがあつた場合においては、家庭裁判所は、最高裁判所の定めるところにより、仮差押え、仮処分、財産の管理者の選任その他の必要な保全処分を命ずることができる。と規定されております。
したがって、家庭裁判所が、保全処分を命ずるには、遺産分割審判の継続が必要になります。
■仮差押え
代償分割による本案審判になる可能性が高い場合になされる。
■処分禁止仮処分
遺産である不動産を取得する可能性が高い相続人が他の相続人に対し、その不動産の共有持分の処分を禁止する場合になされる。
■仮分割仮処分
相続税の納付期限が切迫しているなどの事情がある場合に、預金を管理する相手方に対し、申立人らへ金銭の仮払いを命じた事例(大阪家裁堺支部昭和59年5月28日審判)
相続人の中に行方不明者がいる場合には、その人のために不在者財産管理人を選任して、その不在者財産管理人が遺産分割審判に参加することになります。
問題は、下記のような場合にどのように処理するかです。
①遺産分割審判後に行方不明者が遺産分割前に死亡していたことが判明した場合
②遺産分割審判後に行方不明者が相続開始前に死亡していたことが判明した場合
①の場合は、本来、行方不明者の相続人が遺産分割の当事者となるべきだったにも関わらず、不在者財産管理人が遺産分割審判に参加しているため、その効力が問題になりますが、学説の多くは、不在者財産管理人は、既に死亡している可能性のある本人のために選任されておりますので、遺産分割審判は有効であるとしております。
②の場合は、さらに問題があります。
行方不明者が相続開始前に死亡していたことが判明したということは、そもそも行方不明者は相続人でなかったということになるだからです。
この場合、学説争いはありますが、遺産分割審判を有効とし、不在者財産管理人が管理している遺産を代襲相続人に引渡し、代襲相続人がいない場合には、その遺産を追加的に遺産分割すればよいという説が有力です。
包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有します(民法第990条)。
したがって、遺産の一部について包括遺贈があった場合、遺産の共有関係を解消するために遺産分割をしなければなりませんので、包括受遺者は遺産分割審判の申立をすることができます。
しかし、包括遺贈について、遺言執行者が選任せれている場合には、遺言執行者が遺産分割審判の申立を行うことになります。
遺言執行者が選任されている場合、相続人は遺産の処分権限を持たず、遺言執行者が遺言の執行について一切の権限を有することになるからです。
死後認知者は、死後認知を認容する裁判が確定して初めて相続人になりますので、裁判が確定した後は、遺産分割審判の申立てを行うことができます。
しかし、裁判が確定した時に既に遺産分割が完了している場合には、他の相続人に対し価額請求をすることができます(民法第910条)。
相続人の債権者は、行使上の一身専属権ではない遺産分割請求権を代位行使できるという裁判例があります(名古屋高裁昭和43年1月30日決定・名古屋高裁昭和47年6月29日決定)。
しかし、相続人の債権者は、自己の債権の満足のみに関心があり、遺産の総合的分割に関心がないのだから、債務者の持分に執行することで満足すべきであるという見解もあります。
相続人の債権者は、遺産分割を詐害行為として取り消すことができます(最高裁判例平成11年6月11日判決)
理由としては、遺産分割協議は、性質上、財産権を目的とする法律行為であるということができるからです。
特定の財産が被相続人の遺産に属することの確認を求める訴えは適法です(最高裁判例昭和61年3月13日判決)。
遺産分割審判が確定しても、そもそも、遺産の帰属性が否定されたら、遺産分割審判をした意味がありません。
したがって、遺産分割審判の前提として、遺産の帰属性が確定することによって、遺産分割審判が紛争解決の手段として意義を有することになります。
- はじめての相続入門
- 相続応用知識
- 川崎相続・名義変更相談室について
- 相続による名義変更登記
- 相続放棄
- 相続不動産の売却
ご連絡先はこちら
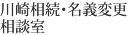
運営:司法書士KAWADAリーガルオフィス 川崎市中原区丸子通一丁目 636番地 朝日多摩川マンション213号室
FAX:044-431-3182
Email: kawada-office@khf.biglobe.ne.jp
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
主な業務地域
■川崎市 中原区、川崎区、幸区、麻生区、多摩区、高津区、宮前区
■横浜市 中区、西区、南区、鶴見区、神奈川区、保土ヶ谷区、戸塚区、泉区、栄区、港南区、瀬谷区、旭区、磯子区、金沢区、青葉区、緑区、都筑区、港北区
■神奈川県(その他) 藤沢市、茅ヶ崎市、鎌倉市、大和市、平塚市、相模原市(中央区、緑区、南区)、小田原市、南足柄市など
■東京都 大田区、品川区、目黒区、渋谷区、新宿区、世田谷区、港区、千代田区、中央区、文京区、台東区、江戸川区、豊島区、杉並区、中野区、墨田区、江東区、葛飾区、足立区、荒川区、板橋区、練馬区など23区全域、町田市など
■千葉県
■埼玉県
ご連絡先はこちら
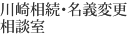
運営:司法書士KAWADAリーガルオフィス 川崎市中原区丸子通一丁目 636番地 朝日多摩川マンション213号室
FAX:044-431-3182
Email: kawada-office@khf.biglobe.ne.jp
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
携帯からはこちら

モバイルサイト
QRコードを 読み取って アクセスできます







